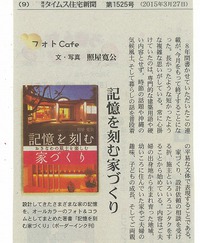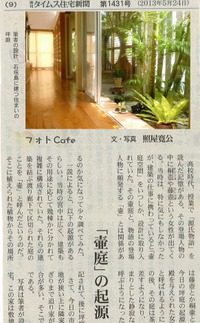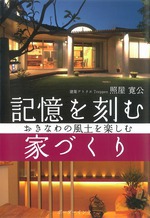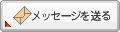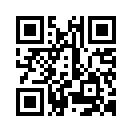2009年10月02日
家に福をもたらす神・・!

月に一度・・
新聞にコラムを書いている。
タイムス住宅新聞『フォトCafe』である・・
今日の新聞に掲載されている
「家に福をもたらす神」の話・・
ご一読ください・・!
↓ランキング・アップ・クリックも
お忘れなきよう・・
よろしくお願いいたします!
家に福をもたらす神
写真・文/照屋寛公
かつての沖縄伝統家屋の棟木には『天官賜福 紫微鑾駕』(てんかんしふく しびらんか)の文字が書かれていた。この由来になった話が石垣島に伝わっている。
昔、川べりに老人が立っていた。ある男がその脇を通り過ぎようとしたら、老人は頼みがあるという。「この川を渡りたいのだが老体の自分には渡れない、背負って渡してほしい」というのだ。男は裸になり背負って川を渡っていると、背中にお腹が当たり、あまりにも熱かったという。何故こんなにお腹が熱いのかと尋ねると、風邪気味で熱があって熱いというのだ。
川を渡り終えると、老人は「ありがとう、実は私は人間ではありません、天からの使いの者です」という。天からどのような使いかと聞くと、何集落の何番地の某家を焼いて来いというものだった。男は驚いた、それは自分の家だったからだ。老人は「背負ってもらって恩義のあるあなたの家を焼くわけにはいかないです。村はずれに小さな小屋を造ってくれたら、それを焼いて、煙で天に昇ります」と言った。
この類(たぐい)の話は沖縄本島にもあって伝承の範囲は広いようだ。しかし、石垣島に伝わる話は助けてもらったお礼に、老人から『天官賜福 紫微鑾駕』の棟札を書いておけば火事から免れることが出来ることを教わるところに特徴がある。その後、この謂(いわ)れが流布し大工の棟梁が家普請で棟木に書くようになったらしい。
この話から分かるのは、住まいが木造であった先人の家屋は、火災を最も恐れたということだ。不思議なことに災害でも台風や地震にまつわる自然災害の伝承はあまり聞かない。火災は火の不始末や思いもよらぬ延焼等で被害をうける人災的要素が強いからであろう。先人は家屋に対して火災を恐れ、火の取り扱いに気を使ったことがうかがえる。
今日では、建築物の構造もコンクリート造になり、報知器など防災設備が充実している。また棟木の存在も目にすることもほとんど無くなってしまった。ちなみに、『天官賜福 紫微鑾駕』は天の神が福を授け、北極星の神が馬車に乗って降りてくる」という意味である。
(建築アトリエ・トレッペン代表・建築家)
カテゴリ→『新聞連載『フォトCafe』
 ↓ランキングアップ状態をチェックできます!!
↓ランキングアップ状態をチェックできます!! 画像多数!ご覧ください。
建築アトリエTreppenのHPへGo!
画像多数!ご覧ください。
建築アトリエTreppenのHPへGo!Posted by 遊悠人 at 13:43│Comments(0)
│『新聞連載『フォトCafe』